記事の目的
企業が扱うデータは年々増加し、その活用方法が事業の成長を左右する時代になっています。営業活動やマーケティング施策の効果測定、顧客体験の改善、経営層の意思決定など、あらゆる場面でデータが利用されています。その中心にあるのがデータウェアハウス(DWH)です。
近年ではクラウド環境で利用できるDWHが主流となり、特にAmazon RedshiftとGoogle Cloud BigQueryは代表的な選択肢として注目を集めています。どちらも大規模なデータ処理を可能にする強力なサービスですが、その設計思想や利用方法、コストモデルは大きく異なります。
本記事では、まずDWHの基本的な役割を整理し、次にBigQueryとRedshiftそれぞれの特徴を解説します。最後に機能一覧表で比較を行い、マネージャーが自社に合ったサービスを選ぶための参考となるようまとめます。
データウェアハウスとは
データウェアハウス(DWH)とは、企業内外に散在するさまざまなデータを一元的に集約・整理し、分析やレポートに活用できるようにする基盤です。通常の業務システムは日々の取引処理やオペレーションに最適化されていますが、DWHは「分析や意思決定」に特化している点が特徴です。
DWHが必要とされる理由
1. 意思決定の迅速化
複数のシステムから集約されたデータを統合的に扱えるため、経営層やマネージャーが迅速に判断できる環境を整えます。
2. 部門横断のデータ活用
部門ごとに分散した顧客データ、販売データ、サポート履歴などを統合し、全社的に共通のデータをもとに議論できます。
3. BIやAI活用の基盤
DWHはBIツール(Tableau, Looker, Power BIなど)や機械学習の土台となり、データドリブン経営を実現する必須要素となります。
4. データガバナンスの確立
データ定義や履歴管理を統一することで、組織全体で「唯一の正しいデータ」を共有でき、信頼性を確保できます。
BigQueryとは
Google Cloud BigQueryは、Google Cloudが提供するサーバレス型のクラウドデータウェアハウスです。フルマネージドサービスであり、インフラの構築や運用を利用者が担う必要はありません。
※Bigqueryのコード画面
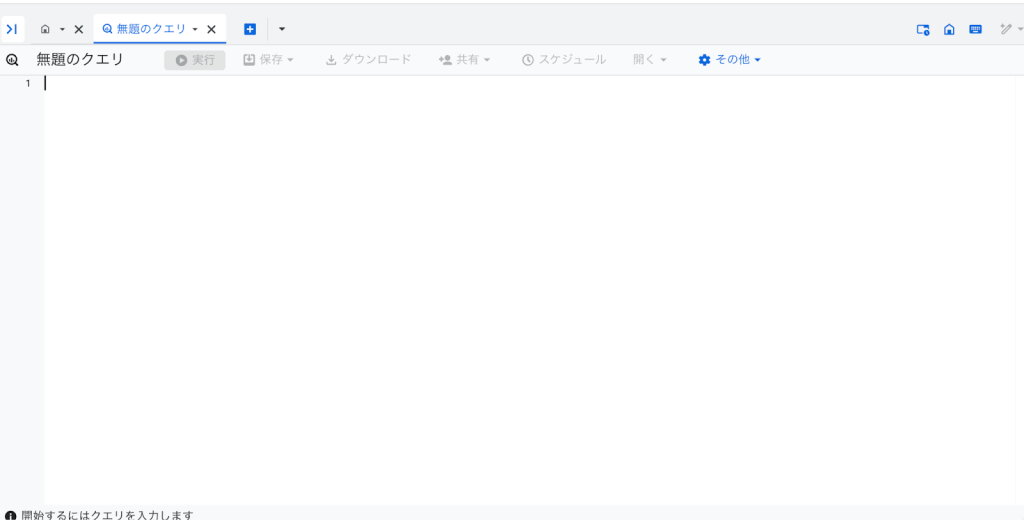
特徴
- サーバレス運用:インフラを意識せず、SQLを書くだけで分析可能
- 従量課金モデル:保存したデータ量とクエリでスキャンしたデータ量に応じて課金
- 高いスケーラビリティ:ペタバイト級データでも自動的にスケーリング可能
- Google Cloudサービスとの統合:Google広告,GA4,Dataflow(ETL)、Looker(BI)、Vertex AI(AI/ML)と容易に連携
※Looker画面からBigqueryとの連携が可能

マネージャー視点のメリット
- 導入が容易で短期間で分析を開始できる
- 運用負荷が小さく、少人数チームでも運用可能
- 新しい施策や仮説検証を素早く実行できる
Redshiftとは
Amazon Redshiftは、AWSが提供するクラウド型データウェアハウス(DWH)であり、クラウドDWH市場の先駆け的な存在です。クラスタ型アーキテクチャを採用し、ノードを構成して性能を確保する仕組みが基本ですが、近年ではより柔軟な利用形態も提供されています。
※Amazon Redshiftのコード画面
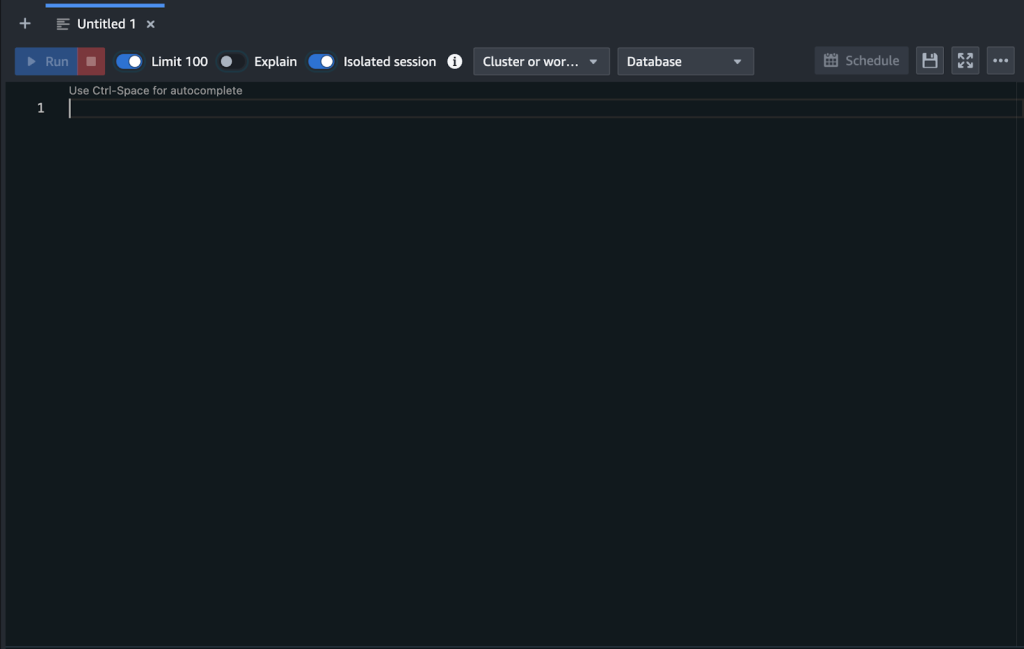
特徴
- クラスタ型アーキテクチャ:ノードを構築して利用する方式。高性能かつチューニング性に優れ、大規模データの安定処理に強い。
- 料金モデル(従来型):インスタンス課金(時間単位)。長期利用では「リザーブドインスタンス」によってコスト削減が可能。安定運用を前提とした大規模組織に適する。
- Redshift Serverless(従量課金型):サーバやクラスタの管理を意識せず、クエリの実行量に応じて課金される方式。利用開始のハードルが低く、小規模導入や変動的なワークロードに対応可能。BigQueryに近い使用感をAWS環境で実現できる。
- Redshift Spectrum:S3上のデータを直接クエリ可能にする機能。DWHにデータをロードしなくても分析できるため、データレイクとDWHをシームレスに統合できる。利用量に応じた従量課金。
- AWSサービスとの強力な統合:GlueによるETL処理、SageMakerによるAI/ML活用、S3によるデータレイク連携など、AWSエコシステム全体と密接に連携できる。
マネージャー視点でのメリット
- 大規模組織に強み:固定費型で安定運用が可能。AWS環境に統合しやすい。
- 柔軟性も確保:Redshift ServerlessやSpectrumにより、小規模利用や従量課金モデルも選択可能。
- 投資対効果の調整が可能:利用規模に応じて「固定費型」と「従量課金型」を使い分けることで、コスト最適化が可能。
機能一覧表(比較サマリー)
| 項目 | Google Cloud BigQuery | Amazon Redshift |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | サーバレス(フルマネージド)、インフラ運用不要 | 基本はクラスタ型(ノード管理必要)、Serverlessでサーバレス利用も可能 |
| 料金モデル | 従量課金(クエリ実行量+ストレージ利用量) | 固定費型(インスタンス課金)、Serverlessで従量課金可、SpectrumでS3従量課金分析 |
| スケーラビリティ | 自動スケーリング、ペタバイト級対応 | ノード追加で拡張、Serverlessなら自動スケーリング可 |
| 運用負荷 | 低い(インフラ管理不要) | 高い(クラスタ型はDBAや運用必須)、Serverlessで軽減 |
| パフォーマンス | Googleインフラによる並列処理で自動最適化 | 列指向ストレージ+分散処理で高性能、詳細なチューニング可能 |
| エコシステム統合 | Google Cloudサービスと親和性(Google広告,GA4,Dataflow, Looker, Vertex AIなど) | AWSサービスとの親和性(S3, Glue, SageMakerなど)、SpectrumでS3直接分析 |
| 導入のしやすさ | 初期導入が容易、利用開始のハードルが低い | クラスタ型は初期設計が必要、Serverlessなら導入容易 |
| 適した組織 | 小〜中規模、スピード重視 | 大規模で安定重視、中小規模でもServerless活用で柔軟対応 |
結論(まとめ)
Amazon RedshiftとGoogle Cloud BigQueryは、いずれもクラウド時代における代表的なデータウェアハウスであり、企業のデータ活用を強力に支える基盤です。ただし、その思想や料金体系、運用モデルには明確な違いがあります。
- BigQuery:サーバレスかつ完全従量課金モデル。運用負荷を最小限に抑え、スピード感を重視したい小〜中規模組織に最適。 Google広告やGA4など様々なGoogleサービスと容易に連携が可能。
- Redshift:固定費モデルで予算計画を立てやすく、大規模で安定したデータ分析基盤を求める企業に適している。 Redshift Serverless / Spectrumを活用することで変動の大きいワークロードやコスト最適化を重視する場合に有効。BigQueryに近い柔軟性をAWS環境で実現可能。
最終的には、「固定費で安定した運用」か「従量課金で柔軟な運用」かという視点に加え、既存のクラウド環境やサービスとの親和性や社内の運用体制を踏まえて選ぶことが重要です。両サービスとも進化を続けているため、小規模な検証(PoC)を通じて自社の利用シナリオに合うかを確認することを強くおすすめします。